なぜかMassiveについて調べると、シンセを学ぶならMassive的なものを見かけます。
なんか、これが基本、みたいな。
ボク的には、シンセはSerumやVitalが一番わかりやすいと思っているんですけど。
Serumとかは後発だから、という理由もあるのかもしれませんけど。
そして、逆にMASSIVEが、わからなさすぎて、嫌なんですけど(笑)
ということで、わからなさすぎるけれども、わかるように見ていきましょう。
まぁ、プリセットを選ぶ方が早いんですけど。
基本情報
ダウンロードはこちら。
インストール方法
Native Accessというソフトからインストール
見た目はこんな感じ。

わからない言葉などが出てきたら、こちらで確認を。
プリセット

Browserをクリックすれば、プリセットの一覧が表示されます。
プリセットを選べば、上に8つのノブが表示されます。
このプリセットで、音を変えたいのであれば、このあたりを変えたいんじゃないですか?という、いわば、プリセット側の提案ですね。
つまり、好みのプリセットを選ぶ、上のつまみでより好みの音にする、というので完結です。
プリセット追加
さらに、Massiveはサードパーティ製のプリセットもたくさん販売されています。
無料でもらえる場合もあります。
それらを購入したら場合の追加方法。
FileからOptionsを選択。

Brouserを選んで、Addをクリックで、プリセットの入っているフォルダを選択すればOKです。

ROUTING

よくわからないから、ルーティングを確認。
ROUTINGというのがあるので、そこで確認できます。
オシレーターが3つとノイズ、フィルター2つ、アンプ、パン、FX・・・
まぁ、概ね、こんな感じでしょうね。
そんな特殊な感じはないですね。
OSC

OSC1~3がオシレーターですね。
Massiveはウェーブテーブルです。
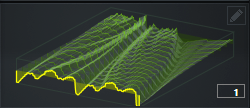
上の画像は、Serumの画像ですが、つまりはこんな感じで、波形の集合体みたいになっているわけです。
OSCで、Squ-SwⅠと表示されているところが、このウェーブテーブルを選択するところです。
Wt-Positionで、ウェーブテーブルのうちの、どの部分の波形にするかを決めます。
波形が見えないので、音で決めるしかありませんね。
まぁ、波形が見えても、波形で音がわかるようにならないと、意味がないから、一緒かもしれませんね。
Intensityで選んだ波形をさらに調整していきます。
上のSpectrumというところを変更することで、Intensityの波形の調整の仕方が変わります。
これらも、何がどうと決まってはいるのですが、もう耳で判断するのが早いでしょうね。
Ampは音量、Pitchはピッチですね。
他のシンセと違って、この部分ではユニゾンとかパンは設定できないようです。
つまり、OSC1を真ん中に、OSC2を右、OSC3を左とかにはできないんですね。
左の青い丸は電源で、ここが消えていると、機能がオフの状態です。
VOICING

なぜかボイシングはここ。
VoicingのMaxは同時に出せる音。
つまり3和音を同時に鳴らせるか、ってことですね。
Unisonoはユニゾンで、1つの音にどれだけ音を重ねるか。
で、ユニゾンもMaxの方に含まれるので、ユニゾンを2にして、Maxを2にすると、ドとミを同時には出せなくなります。
monophonの場合、和音は出せなくなります。
ただ、Unisonは複数でOK。
Monorotateは、ドとソを同時に押し続けると、ド・ソ・ド・ソと交互になるという謎仕様。
いつ使うんでしょう。
Trigerはキーを押したときに、モジュレーションがリセットされるか、続きで動くかみたいなやつです。
Unison Spreadは、Unisonした音をどのように出すかですね。
MODULATION OSC

オシレーター専用の揺らす系(笑)
ここも、音をつくるために、設定します。
どのオシレーターに適用するか選んで、つまみを回す感じ。
OSC

なぜか、オシレーター関係が散ってる感じ。
このあたりが、よくわからんのですよね。
Glideは違うキーの音を鳴らしたとき、パッと音が変わるか、ムニョーンと変わるかってやつですね(笑)
Pitcbendはピッチベンドを動かしたときのピッチの動く範囲。
MIDIとかで操作するときや、オートメーションをかくとき用かと。
Oscillator Phasesは、各オシレーターの位相を設定するところ。
これは、結構重要だと思う。
Vibratoはビブラート、Internal Envelopeはエンベロープ。
KTR OSC

ここにもオシレーター関係。
これも、何に使うのかよくわかりませんが、見た通り、キーを押したときに出る音を設定するわけですね。
まぁ、キック的に、どのキーを押しても、OSC1だけは、低い音だけを出すというのに使えなくもないのかな。
NOISE

忘れていたノイズ。
まぁ、ノイズです。
Whiteと書いているところで、ノイズの種類とColor、Ampで音量を選べます。
少しノイズを足すのであれば、ここです。
Filter

フィルターは、Noneと書いているところで、フィルターの種類を選んで、設定をするだけなので、詳しくは書きません。
それよりも、OSCの横にある、F1、F2と書かれたつまみですね。
これは、F1側につまみを動かすと、Filter1に送られるという意味です。
当然、F2はFilter2。
で、Filterの左に、Ser.⇔Par.というのがあります。
これが、Serはシリアルで、音はFilter1→Filter2と流れるようになっています。
Par.はパラレルで、Filter1とFilter2は並列で流れます。
で、右側にはMixがありますが、Mix1はFilter1から出た音、Mix2はFilter2から出た音になります。
ということは、
Ser.側に最大限に動かして、Mix2側に最大限に動かした場合、音は、Filter1→Filter2→Outとなるわけです。
Ser.側に最大限に動かして、Mix1側に最大限に動かした場合、音は、Filter1のみを通って、Outに出てきます。
例えば、Filter1でローパス最大、Filter2でハイパス最大にして、シリアルにしたら、Filter2を出るときには、音が出ないですよね。
けど、Mix1に方にすると、Filter1の音がOutに出てきますので、音が聞こえます。
このあたりは、色々工夫できる感じですね。
AMP・FX

アンプとエフェクターですね。
Panはパンですし、FXはエフェクターですね。
INSERT

これは、どこにでも挿せるエフェクターですね。
一般的には、だいたいの音の流れが終わって、最後にエフェクターって感じですが、Massiveは挿す場所を選べるんですね。
もちろん、エフェクターの種類は限定ですが、ROUTINGで、自分で選ぶんですね。
これは面白いですよね。
FEEDBACK

これもINSERT同様、ルーティングにとらわれないやつです。
というのも、オシレーターから出て、フィルターがかかった後の音を改めて戻してきて、発信するとか、とにかく一度出したものも、もう一度引き戻して、出すという、なかなか面白いもの。
これもROUTINGで設定できます。
モジュレーション

で、シンセと言えば、モジュレーション。
ENV4種類、LFO2種類、Performer2種類、STEP1種類。
十字矢印をつまみの下の四角に持っていくことで、割り当てる形です。
ここも、色々なカーブを選んだり、設定はいくらでもできるので、楽しいところですね。
MACRO CONTROL

これは、マクロ用ですね。
プリセットで用意されていたようなマクロつまみの設定ですね。
まとめ
しっかりみていくと、なかなか面白いシンセですね。
ただ、どうやったって、わかりづらい。
なんだろうなぁ、このわかりづらさは。
価格
【定価】
99ドル
【セール等の価格】※全てのセールを把握しているわけではないので、参考までに・・・
2023年8月 3866円(PLUGINBOUTIQUEさん)
2023年8月 9722円(PLUGINBOUTIQUEさん)
2023年12月 41.5ドル(PLUGINBOUTIQUEさん)
2024年5月 3285ドル(PLUGINBOUTIQUEさん)
2024年6月 19ドル(Plugin Allianceさん)
2024年9月 19ドル(PLUGINBOUTIQUEさん)
2024年12月 2900円(Media Integrationさん)
2025年2月 2900円(Media Integrationさん)
2025年5月 24.75ドル(本家さま)
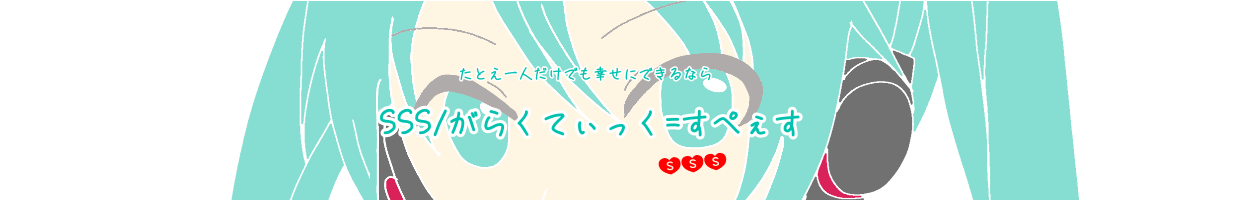



コメント